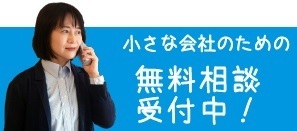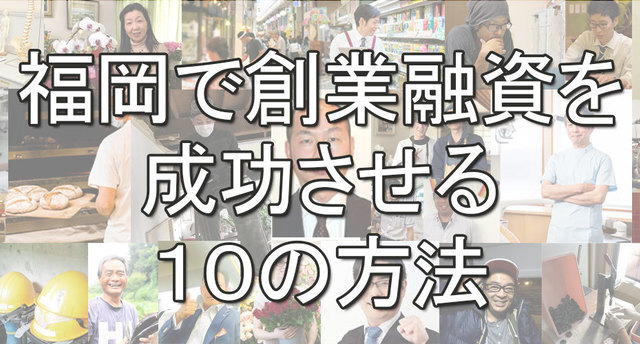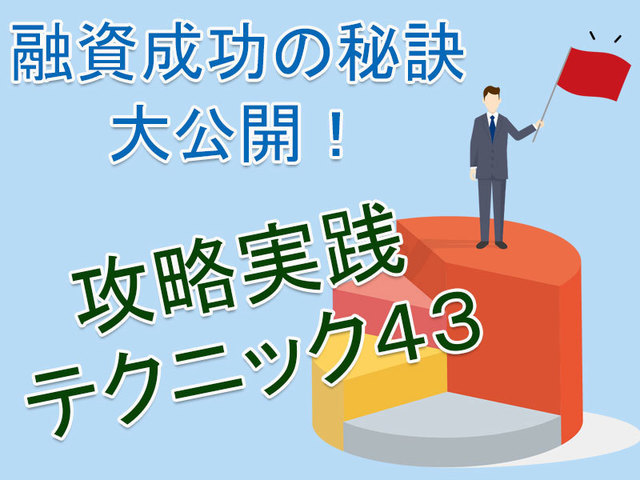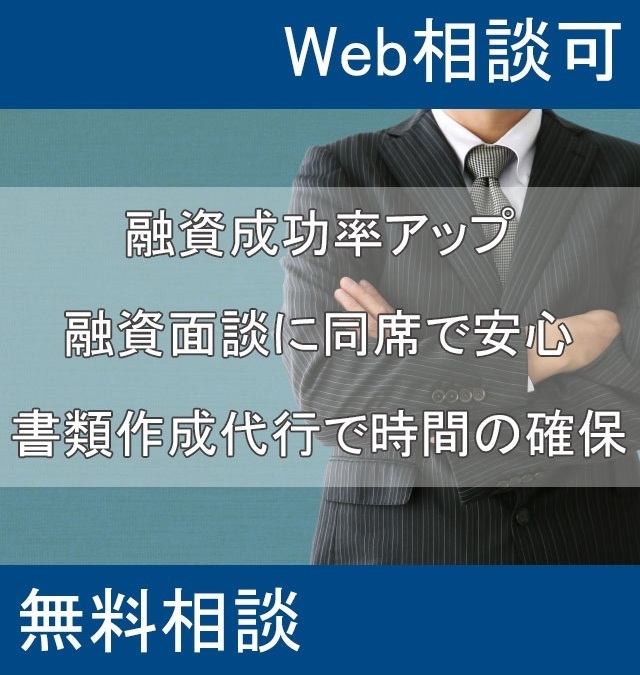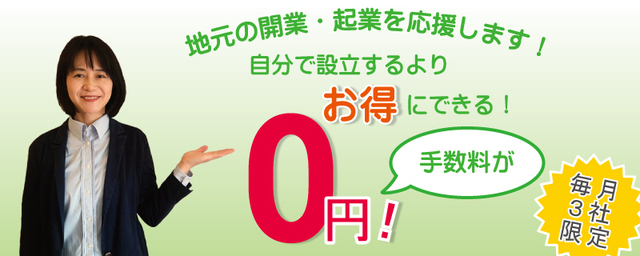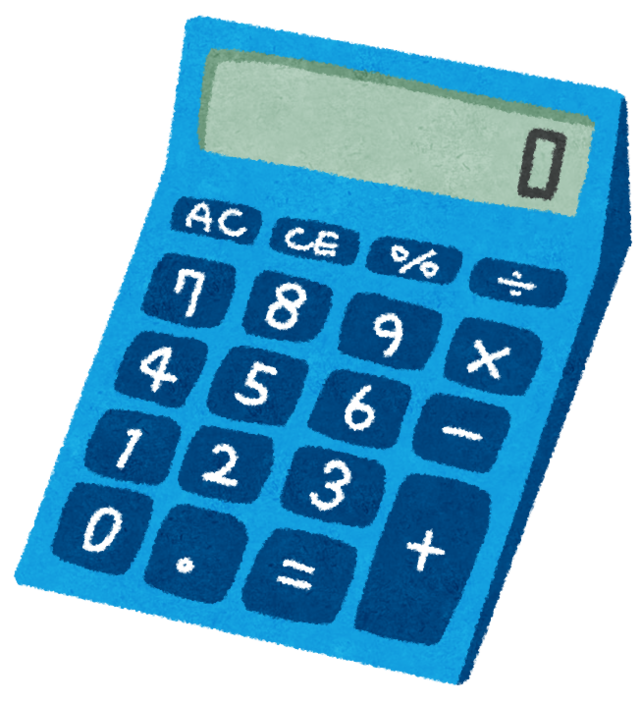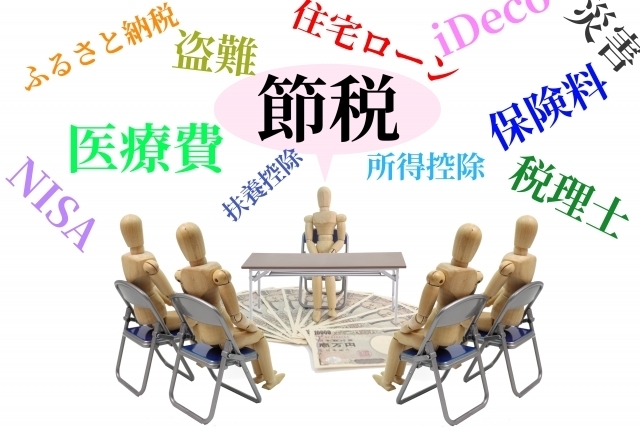経営者にも退職金を!
小規模企業共済当社の特徴
制度の特徴
国が定めた制度で安心!確実!全国で約4割の経営者が加入!
法律(小規模企業共済法)に基づく共済制度、国が全額出資する
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営。
掛金は全額所得控除で節税! 月額1000円~!
払い込んだ掛金は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除欄にご記入頂ければ全額所得控除となり、掛金は月額1000円~7万円の範囲(500円単位)で設定できます。
受け取り時も税制のメリット!
共済金は廃業や退職時のほか、65歳以上で180か月以上掛金を納付した方も受け取り可能。受け取りは「一括」「分割」「一括と分割の併用」に加え、税制のメリットがあります。
世代別のポイント
若手経営者・創業者間もない経営者
 事業規模が小さいときに加入
事業規模が小さいときに加入
小規模企業共済(本共済)加入後、常時使用する従業員が増えて加入資格を失っても、本共済に加入し続けることができます。事業規模が大きくなり加入資格を失う前に、少額の掛金(月額1000円から)で、加入すれば、その後事業規模が大きくなっても続けられ、掛金の増額も出来ます。
 事業資金に困ったら…
事業資金に困ったら…
事業資金に困ったら、掛金納付月数により掛金の7割~9割の範囲内で貸付制度がご利用でき、速やかに資金調達ができます。また、共済金等の請求権は差押えが近視されています。
 退職所得控除を増やせる
退職所得控除を増やせる
共済金受取時の税制メリットである退職所得控除額は、掛金の代償に関係なく掛金納付期間が長いほど大きくなります。若いうちに少額掛金で加入し、退職所得控除額を増やしましょう。
 廃業時の事業の再建等
廃業時の事業の再建等
本共済は、生活の安定や事業の再建を図るために資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。やむを得ず廃業する場合などに、最も有利な共済金Aが受け取れます。
40~50歳前後
 老齢給付で共済金を受け取り
老齢給付で共済金を受け取り
50歳までに加入すれば、65歳の年金受給開始時に老齢給付で共済金Bを受け取ることができ、年金の不足分を補完出来ます。しかも事業を継続しながら受け取れます。また、一度共済金を受け取った後に最後加入することも出来ます。
60歳前後
 加入は年齢制限なし
加入は年齢制限なし
60歳を過ぎても現役で仕事をしていれば本共済に加入できます(年齢制限なし)。会社役員等
平成28年4月の法改正により65歳以上で任意に退任した場合でも、有利な協最近を受け取れるようになりました。
加入済みの方へ
今の掛金の増額で、節税を考えてみませんか?
掛金の増額は五百円単位で、掛金の上限7万円まで増額でき、掛金全額が所得控除されます。掛金月額の増額申し込みは、「掛金月額変更(増額)申込書」に必要事項を記入のうえ、窓口でお申込みいただきます。
さらに、平成28年4月の法改正により、現金なしでも増額のお手続ができるようになりました。
 共同経営者の加入
共同経営者の加入
現在加入の個人事業主に加え、配偶者や後継者等の共同経営者は、条件を満たせば2人まで加入できます。
 会社等の役員の加入
会社等の役員の加入
事業資金に困ったら、掛金納付月数により掛金の7割~9割の範囲内で貸付制度がご利用でき、速やかに資金調達ができます。また、共済金等の請求権は差押えが近視されています。
現在加入している役員のほか、取締役や監査役など商業・法人登記簿謄本等に登記がある会社等の役員は、加入できます。
加入資格
次の2つの条件を満たす方が加入できます。
- 個人事業主及びその共同経営者又は会社等役員(登記があること)
- 常時使用する従業員人数の条件が以下を満たしていること
- 小売業・卸売業・サービス業等…5人以下
- 製造業・建設業・運輸業・農業等…20人以下
- 宿泊業・娯楽業…20人以下
※「常時使用する従業員人数」は、雇入期間の定めのあるパートやアルバイト等の従業員及び個人事業主、共同経営者、専従者並びに会社役員は含まれません。
共済金のよくあるご質問
ここではよくあるご質問をご紹介します。
ほんとうに安心・確実なの?
小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度です
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
個の制度に加入できる人は?
小規模企業共済制度に加入できるのは、次の方です。
- 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の起業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員
- 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で①②をともに満たす方となります。
- 「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
- 「事業の執行に対する報酬を受けている」
毎月の掛金はどのくらいなの?
掛金月額千円~7万円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
また、払込方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。
掛金は税法上どんなメリットがあるの?
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です)
※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2税額は、平成28年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割りについては、5000円としています。
※3節税の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用ください。
共済金の税法上の取扱いは?
共済金の受取りは、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかをお選びいただけます。
税法上、一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
事業資金も借り入れできるの?
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。(担保・保証人は不要)
【貸付の種類】
一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け
共済金の受給権は?
共済金・解約手当金の受給権は、国税等滞納の差押え以外は、差押禁止債権として保護されます。
詳しい共済金について
掛金の全額所得控除による節税額の一覧表
| 課税される所得金額 | 加入前の税額(a) | 加入前の税額(b) | 節税額(=a-b) | ||||
| 所得税+住民税 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | 掛金月額1万円 | 掛金月額3万円 | 掛金月額7万円 | |
| 200万 | 309,600 | 288,900 | 252,700 | 180,200 | 20,700 | 56,900 | 129,400 |
| 400万 | 785,300 | 748,800 | 675,800 | 544,000 | 36,500 | 109,500 | 241,300 |
| 600万 | 1,393,700 | 1,357,200 | 1,284,200 | 1,138,100 | 36,500 | 109,500 | 255,600 |
| 800万 | 2,034,200 | 1,994,100 | 1,913,700 | 1,753,000 | 40,100 | 120,500 | 281,200 |
| 1000万 | 2,806,000 | 2,753,600 | 2,648,700 | 2,439,000 | 52,400 | 157,300 | 367,000 |
※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2税額は、平成28年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
※3節税額の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用下さい。
共済金等の受取り
| A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | |
| 個人事業主 | ◎個人事業の廃止(※1) (注)複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件となります。 ◎個人事業主の死亡 | ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) | ◎法人成りし、その会社役員に就任しなかった(※4) ◎法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く)(※4) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除(12ヶ月以上の掛金滞納等) ◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった(※4) |
| 共同経営者 | ◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任(※2) (注)事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件となります。 ◎共済契約者の死亡 ◎共同経営者の疾病又は負傷による退任 | ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は受給権を得ます) | 役員に就任しなかった ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く) | (12ヶ月以上の掛金滞納等) ◎個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった ◎共同経営者の退任による解約 |
| 会社役員等 | ◎会社等の解散 (注)組織変更により会社を解散した場合を除きます。 | ◎会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任(※3) ◎会社等役員の死亡 ◎老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます) | ◎会社等役員の退任(疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散を除く) | ◎任意解約 ◎中小機構による共済契約の解除 (12ヶ月以上の掛金滞納等) |
※1平成28年3月以前に「配偶者又は子へ事業を全部譲渡」したときは準共済事由となります。
※2平成28年3月以前に「個人事業主の配偶者又は子への全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶又は子へ事業を全部譲渡(共同経営者の地位譲渡)」したときは、準共済事由となります。
※3平成28年3月以前に「疾病又は負傷以外の事由による退任」をしたときは、準共済事由となります。
※4平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りしたときは、A共済事由となります。(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一通算・承継通算手続をした方を除く)
共済事由と掛金納付年数に応じた、共済金受取額及び税法上の取扱い
掛金月額が10,000円の場合 例えば掛金月額を30,000円として試算するときは、下表の金額を3倍にしてください。
| 掛金納付年数 | 掛金合計 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
| 5年 | 600,000 | 621,400 | 621,400 | 600,000 | 掛金納付月数に応じて、 掛金合計額の80~120% 相当額がお受取りいただ けます。掛金納付月数が、 240か月(20年)未満の 場合は、掛金合計額を下回 ります。 |
| 10年 | 1,200,000 | 1,290,600 | 1,290,600 | 1,200,000 | |
| 15年 | 1,800,000 | 2,011,000 | 2,011,000 | 1,800,000 | |
| 30年 | 2,400,000 | 2,786,400 | 2,786,400 | 2,419,500 | |
| 税法上の取扱い | 退職所得扱い | 一時所得扱い | |||
※1共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。
※2A・B準共済金の額は源泉徴収前の共済金額等の額です。したがって掛金月額及び契約期間によっては、手取り額が掛金合計額を下回る場合があります。
※3解約手当金の税法上の取扱いについては、任意解約で解約時65歳以上の場合、共同経営者の退任による解約で退任時65歳以上の場合、および法人成りによる解約の場合、退職所得扱いとなります。