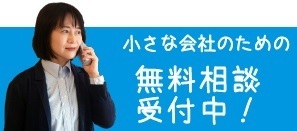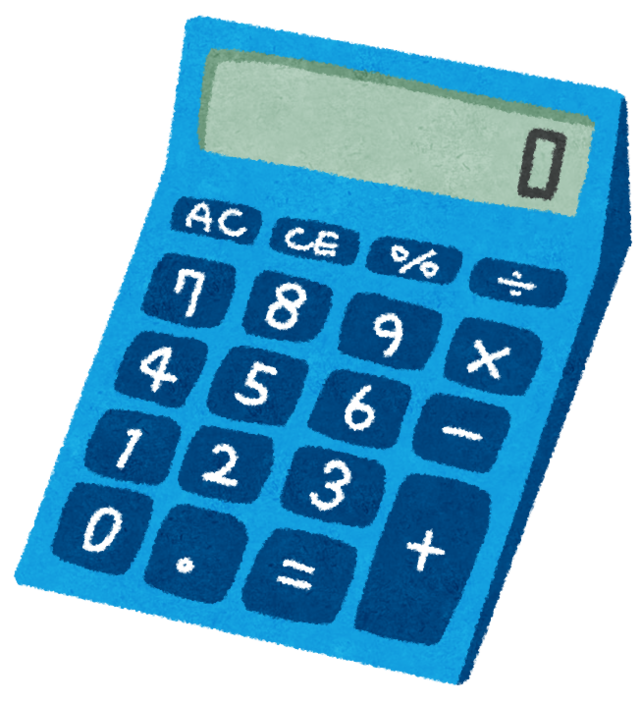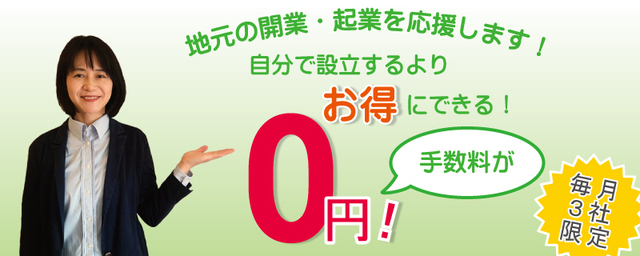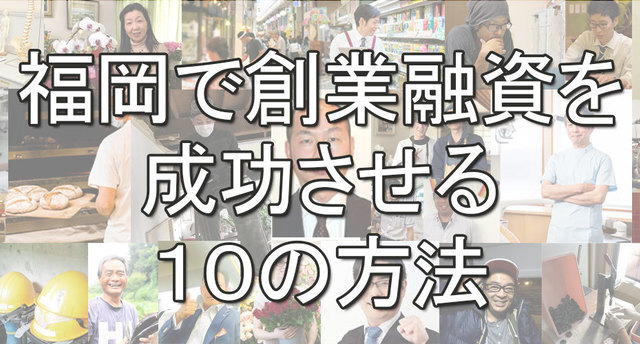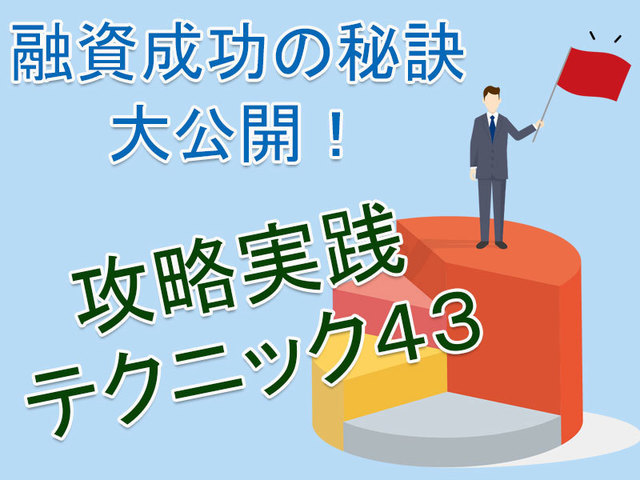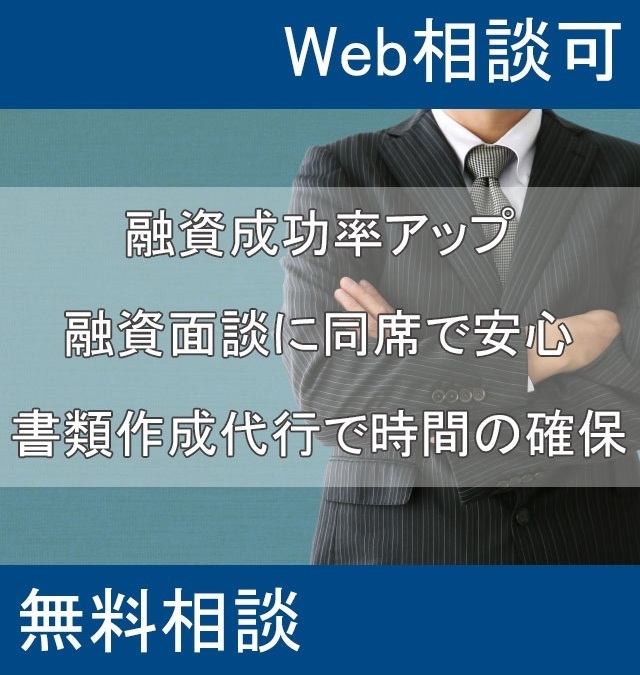2回目のコロナ融資(追加融資、借換)を通すための有効な方法(3/3)
(挨拶)
このメールは、3通目/3通になります。合わせてお読みいただくとより自社の経営の安定化につながると思います。
1通目:「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の期限が2022年6月末まで延長します。
2通目:苦しいときは、〇〇(借換)も視野に入れよう。
3通目:2回目のコロナ融資を通すための有効な方法 *当メールです
最近、当事務所でも、返済開始とともに資金繰りの相談が増え始めています。
「公庫や取引金融機関に、コロナ融資を申請したが断られた」
1回目の申請で
「「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は簡単に借りることができる」と簡単に考え、2回目の申請では融資を断られた事例が増えています。
断られた企業は以下の3点が共通しています。
・「決算書、試算表」の2点だけの資料提出
・資金が枯渇しそうになってから、「融資を急いでほしい」と依頼
・経営者の自社評価と銀行の財務格付けがずれている
2回目の融資はこれでは、チャンスを逃してしまいます。
2回目の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請は、1回目の申請に比べて格段にハードルが上がります。
2回目の申請では、1回目の申請で求められていなかった資料を提出しなければ
審査に通りにくいのです。
(*厳密には、1回目が政府の指示もあり、特別な状態だったということになります)
特に、財務格付けが低く、資金繰りに悩む企業にとってその傾向は強くなります。
(本文)定期訪問と事業計画書等を準備しましょう。
〇事業計画書が必要な2つの理由
金融機関が融資する際には、数字を重要視するのはいうまでもありません。
そのため、「決算書」や「試算表」の提出を担当者から求められ提出する流れとなります。
業績の良い企業であればこの2点の内容もよいため、それらだけで「返済可能性も高い」と判断してもらえます。
しかし、業績があまり良くない会社ではどうでしょうか?
業績が良くない会社の「決算書」や「試算表」は当然よくないため、それらだけでは「返済可能性が低い」と判断されてしまうのです。
そこで、過去を表す「決算書」や「試算表」だけでなく未来(将来の可能性)を表す「事業計画書」を提出することが融資を有利に運ぶカギとなるのです。これが事業計画が必要な1つめの理由です。
2つ目の理由は、金融機関の融資審査という構造からの理由です。
融資審査を行うのは融資申請を行う担当者ではありません。担当者は、融資を希望する企業から、資料を受け取った後、稟議書という書類で、融資審査部署に申請を出します。
そのため、いくら口頭で伝えても、事業内容をよく理解していない者が、一度聞いただけで、その内容を稟議書に反映させることはできず、結局有効な稟議書が作成できずに審査された結果、融資が通らなかったということになるのです。
口頭でなく、事業計画書という書面を渡しておけば、それが稟議書に加えられ融資審査を受けることになります。
事業計画書(返済できる根拠)を伝える資料がある融資審査とない融資審査どちらが有利かはいうまでもないでしょう。
〇事業計画書を作った後はどうする?
事業計画書は作って終わりではなく、
・毎月予実管理(計画と実績の比較)を行い
・定期的(できれば1か月に1回)に銀行に事業計画書と実績(試算表)を持っていって説明する。
とセットで考えてください。
事業計画を作るだけでも経営上様々な効果を得ることは可能ですが、その後、金融機関に持っていき業績報告することで、融資確率を上げることが可能となります。
(補足:こちらも重要な考え方になります)
その1:政府の下支え策は永遠には続きません。
日本公庫では、将来の貸倒見越し額が、リーマンショックの際の水準に匹敵しているといわれています。つまり、融資額はかなり大きく膨れ上がっているため、ここ数年の特別な緩い審査による融資は減少し、今後は保証協会融資や公庫融資が容易には受けられなくなる可能性が高いということです。
また、金融機関は「自助努力をする企業を支援」という姿勢へ変化しつつあります。ここでいう「自助努力する企業」というのは、その努力が金融機関に伝わっているということです。つまり、金融機関に対してこのように努力していますよとアピールする資料(事業計画書)が必要になります。
その2:返済額増加を考慮した資金繰りに注意を払いましょう。
返済額が大きければ大きいほど、利益とキャッシュの動きがずれていきます。
現在融資を受けられている企業のみなさまは、返済額増加を考慮した資金繰りに注意を払って経営を進めましょう。特に「いつ資金が枯渇するのか」「いつ再度資金調達が必要か」「この投資は実現可能か」等については、資金繰表を作成して把握しておきましょう。
その3:情報提供料と融資の成功確率は比例します。
何度も会う中で、次のような様々な資料提出をすることで金融機関との信頼関係が構築されていきます。「資金繰り表」「借入金一覧表」「見積書」「契約書」「予想損益計算書」等の様々な説明資料を提出することが重要です。
その4:駆け込み融資依頼=管理できない経営者とみられています。
定期訪問の大きな目的のひとつに、自社の現状を知らせ「いつ頃次の融資が発生
しそうだ」ということを知ってもらうということがあります。もし、あなたが融資するとしたらどちらの顧客に融資したいと思うでしょうか。
A:「融資は今すぐというわけではありません。半年後か1年後ぐらいです。その間毎月業績報告を行いますのでその結果を見ていただいてからでも構いません」
B:「資金が枯渇しているのですぐに融資して欲しい」と資金調達を急ぐ顧客
Aさんにだったら融資したいと思いませんか?
Bさんのような顧客は、体よく断りしばらく様子を見る傾向があります。なぜなら金融機関は、資金調達を急ぐ顧客に融資すると返済が焦げ付く可能性が高いことを経験上知っているからです。
今回は、2回目のコロナ融資を受けるための具体的なポイントについてご説明しました。
上記方法を実践することで大きな融資額を引き出している企業は多くあります。
ぜひ、コロナ融資だけでなく、資金調達を検討されている方はぜひ参考にしてください。
福岡で次のようなお悩みはお気軽にご相談下さい。
小さな会社(中小企業や起業家)と個人事業主の開業と成長安定を格安でサポートします。 ご相談内容:開業・資金繰り・融資相談・創業融資・確定申告・会社設立(法人設立)・税務会計業務・経営コンサルティング 会社設立(法人設立):株式会社、合同会社、一般社団法人等に対応しています。
~弥生会計をお勧めしています~
弥生会計は、日本全国で一番利用者が多い会計ソフトです。バランスがよくクラウドにも対応しており初心者でも安心して簡単に操作できます。
小さな会社には、弥生会計、弥生給与オンライン、MISOCAの組み合わせがとっても便利です。料金も安くて安心して利用可能です。