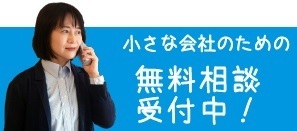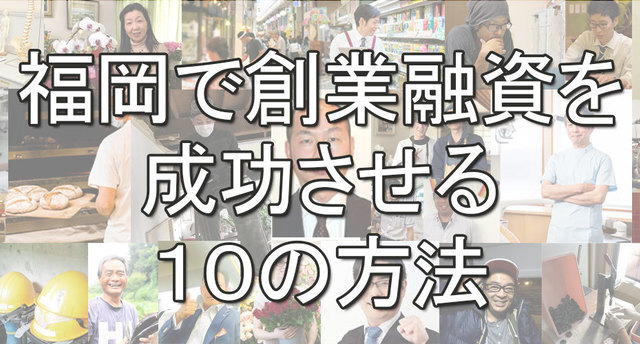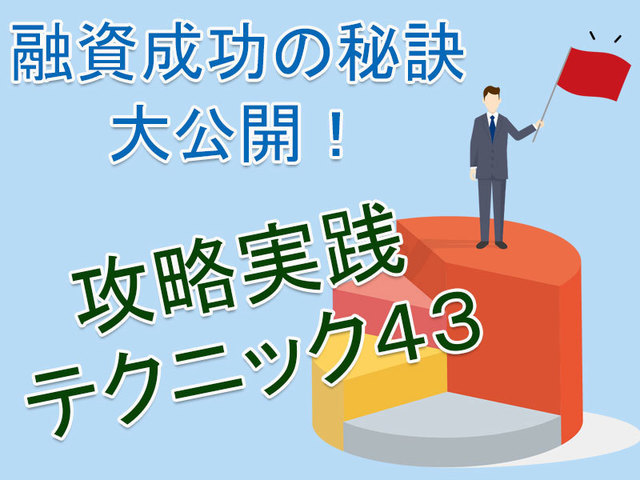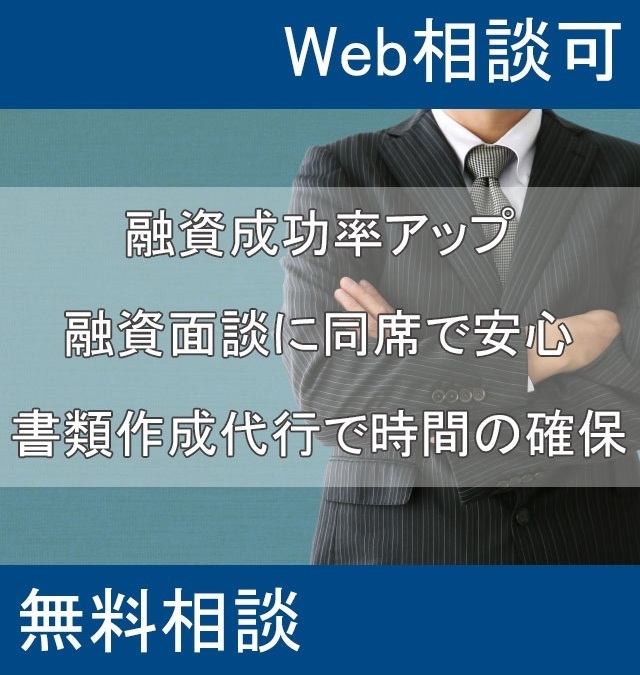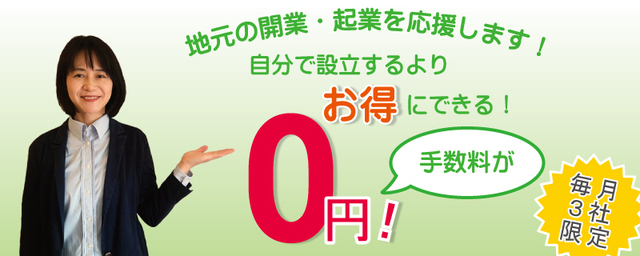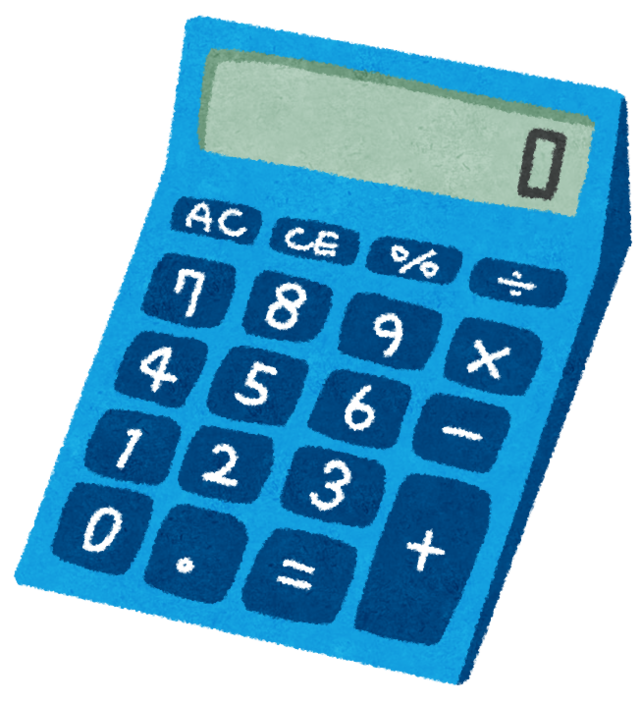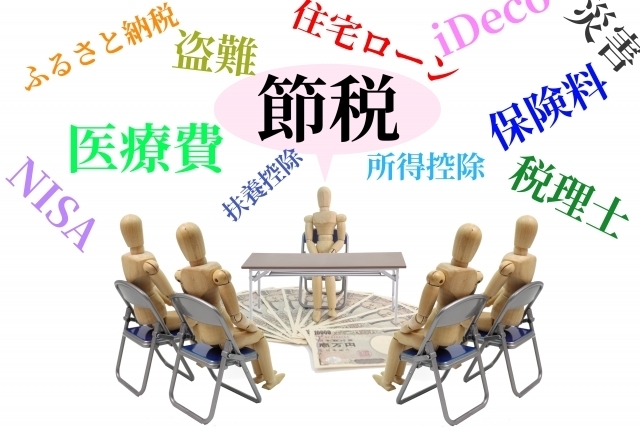合同会社を作るうえでの注意点
企業を相手に事業を行う場合
一般消費者を相手に展開する事業であり、比較的小さな会社であれば合同会社という形態は十分に力を発揮します。合同会社はやはり社会的な認知がまだまだ弱い部分があるため、企業を相手に事業を展開する業種業界では、株式会社のほうが、合同会社よりも信用力は高いと思われている可能性があります。
この点、一般消費者向けの事業ですと、一般消費者の方は、企業に比べて会社の形態で信用力を判断するということは少ないため、法人の形態が法人経営にほとんど影響を与えないためです。もちろん、企業を相手に仕事をされていても特に、取引先が法人形態等に制限を設けてない場合はそれほど大きな問題ではないかもしれません。
合同会社の定款のポイント
①事業目的
事業目的とは、簡単に申し上げますと会社を設立した後に実際に行う事業のことです。また将来的に行う可能性のある事業も記載します。
事業目的は、必ず決めなくてはいけません。少ない会社で2個くらい、多い会社ですと30個以上事業目的を記載している会社もあります。将来行うかもしれない事業も目的として多めに記載しておくのが良いでしょう。
事業目的を追加・修正する場合には、3万円の費用を法務局へ支払う必要がありますので
出来る限り会社設立時点で記載することが効率的です。
②出資者
合同会社では、資本金を出す人を「社員」といいます。一人でも複数でも設立することができます。株式会社では、所有と経営の分離が前提となっているため、出資者と経営者が別でも問題ありませんが、合同会社の社員は、原則出資をするだけではなく経営にも関与します。(所有と経営の一致)そのため合同会社の社員の決定は非常に重要です。合同会社は、原則的には所有と経営が一致していますので、お金を出した人は原則、会社の業務を行っていくことになります。
この会社の業務を行っていく社員のことを業務執行社員といいます。業務執行社員は、会社の経営上の意思決定をしていく社員のことです。
例えば、新しく合同会社を設立し2人が資本金を出すことになった場合、この2人が社員になります。
さらに、原則としまして、この2人が業務執行社員となりまして、さらに、代表社員にもなります。
これは、あくまでも原則的な形となります。といいますのも、株式会社のように、お金を出したいが、経営はしたくないといった人もたくさんいます。
株式会社の場合には、所有と経営が分離していますので、お金を出す人という役割と経営という役割は分離していますので、お金だけを出す人もいます。
合同会社の場合は、原則的には、所有と経営は一致していますが、定款などで定めることによっては、株式会社でいう株主のような役割の社員を設定することができます。
このお金だけ出す人を、単純に社員といいます。社員は、原則的に業務執行社員になることが予定されていますが、定款で業務執行社員としてなりたくない場合には、
業務執行社員にならなくする制限をかけることができます。
ここまでのご説明をまとめますと、社員は3種類あります。
- お金だけ出すだけの社員=社員
- お金も出す+業務をする社員=業務執行社員
- お金も出す+業務をする社員+会社を代表する社員=代表社員となります。
原則的には、合同会社の場合には社員皆が代表社員になることが想定されています。
しかし、会社の代表が複数人いるとなりますと、取引先などは誰が会社を代表しているのか少々混乱します。
そのため、実際には代表社員を1人に絞る会社さんが多く存在します。
③資本金
資本金とは、社員(出資者)が会社に出すお金のことです。資本金は会社に提供しましたら基本的には返ってこないお金です。
資本金は会社の運転資金など会社が事業をする中でに使われます。現在は、資本金の最低金額は1円からとなっておりますので、会社設立の敷居は低くなったといえます。
(会社法が改正される前では、株式会社の場合資本金が1000万円ないと会社を設立することができませんでした。)
資本金をいくらに設定するかは一つ皆様が迷われる事項です。
資本金は1円からできますが、なかなか1円で設立される方は少ないでしょう。資本金=会社規模(=信用)を確認するひとつの指標とされているためです。
設立されたばかりの会社には信用はありません。ビジネスは信頼の世界で成立しています。
そのため会社に存在する多くの取引先は、設立されたばかりの会社の信用を資本金で判断しています。そのため、信用という観点では資本金は多いに越したことないのです。
ただし、消費税の観点からは資本金は1000万円未満をおすすめしています。
資本金が1000万円未満ですと、会社設立2期目まで消費税が免税となるからです。
資本金を1000万以上とした場合は、会社設立初年度から消費税の納税義務が生じます。
④許認可事業
資本金の要件をクリアしていなければ許認可を受けられません。せっかく会社を設立してもそのままでは事業を始められない事態もありえるのでそういった意味で、資本金の額は重要になってきます。許認可は業種や業態によって細かく規定されていますので、設立後の事業に支障をきたさないよう、事前に業界団体や申請先へ問い合わせるようにしてください。
⑤商号
商号とは、会社の名前のことです。会社の名前ですので、基本的には一生名乗ります。
人の名前のように何かしら想いのある名前をつけれたらよいです。商号には、商号を決めるにあたって少しルールがあります。
商号には記述の方法と利用することができる文字体が決まっているのです。
記述の方法としましては、必ず「合同会社」という文字を商号の前後どちらかにつけないといけません。
使用できる文字についても制限があります。使用できる文字については、以下のものになります。
・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(小文字、大文字)・アラビア数字(0123456789)
・符号「&」「’」「・」「,」「.」「‐」となります。
また、有名な会社の商号を使用することなども禁止されております。
⑥本店所在地
本店所在地とは、会社の住所のことです。住所としまして、法務局へ本店として登記した場所になります。
本店の場所と実際の活動の場所は異なるといったケースもあります。
<本店所在地について注意しなくてはいけないこと>
○本店所在地の住所の記載は省略してはいけません
「福岡県福岡市西区1-7-4」のように省略してはいけません。1丁目7番4号のように正式な住所を記載します。
○定款上、最小行政区画の記載でもOK
「福岡県福岡市早良区」までの行政単位の区画のこと最少行政区画といいます。定款上は、全ての住所を表記しても、最少行政区画までの表記でもどちらでも構いません。
しかしあくまでも最小行政単位だけの表記であっても問題ないのは、定款上のお話でして、実際に法務局へする登記については本店の全ての住所を正確に届け出る必要があります。
最少行政区画までの記載にしておくと良いことがあります。
例えば、建物の名称が変わったり、階を移動する、また本店を同じ行政区内(渋谷区⇒渋谷区)で移転する場合に、定款を変更する必要がなく、
また法務局へ支払う法定費用を安く済ませることができる可能性があります。そのため、定款上は通常最少行政区画までの記載になっております。
*その代わり、登記申請時に本店所在地決定書という書類を一緒に提出します。
原則的には、合同会社の場合には社員皆が代表社員になることが想定されています。
しかし、会社の代表が複数人いるとなりますと、取引先などは誰が会社を代表しているのか少々混乱します。
そのため、実際には代表社員を1人に絞る会社さんがかなり多いです。